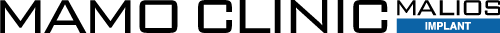歯がなくなってしまった場合、どのような治療の選択肢があるのかあなたは知っていますか。
この記事では、歯が無くなってしまう原因とその際の治療法などについて解説しています。
歯がなくなってしまう原因

歯がなくなる原因にはどのようなものがあるのかをまずは解説します。
厚生労働省が2018年に全国の2,345もの歯科医院を対象に行った全国抜歯原因調査の結果によると、歯が失われる原因で最も多かったものは「歯周病」で37%、その次が「むし歯」で29%、続いて、「破折」(18%)、「その他」(8%)、「埋伏歯」(5%)、「矯正」(2%)というものでした。
このうち「破折」は、外傷などの物理的な大きな力によって作用したものではなく、神経をとった歯(無髄歯)が欠けたものです。
むし歯によって神経を取って破折する、と考えると歯を失う原因がむし歯によるものは47%になります。
つまり「歯周病」が37%、「むし歯」が47%で合わせると84%となり、歯を失う原因はこの二大要素によって占められているのです。
また全体的に「奥歯」から失われる傾向が高く、その影響で前方にある歯は噛み合わせを保持できず「歯並び」にも大きな影響を及ぼします。
歯並びが悪いと「出っ歯」になったり、歯が傾いたりして、さらに歯が失われやすくなる口腔環境になるという悪循環を生んでしまうようです。
歯がなくならないようにするために

口腔衛生学会雑誌による「歯の喪失リスク要因に関する研究」の内容と、先述した歯が失われる多くの原因から、喪失するリスクが高い歯は以下のような歯だと考えられます。
- 未処置のむし歯
- クラウン(冠)が装着されている歯
- 部分入れ歯の針金がかかっている歯(鈎歯)
- 歯周病疾患が進行している歯
クラウン(冠)が装着されている歯ですが、この治療法そのものが喪失リスクを高めるという訳ではありません。
クラウンが装着されている歯は無髄歯である可能性が高く、歯根の先(根尖部)に病変が残ってしまっている場合が多いことから喪失リスクが高いのです。
むし歯が進んでいるために神経をとる治療をしたり(抜髄)、歯根の治療(根管治療)が行われたりした歯は、治療により相当ダメージを受けたことになります。
治療しても健康な歯にくらべるともろくなってしまっているので、そのような状態にならないよう歯を守ることが、歯の喪失を防ぐために非常に重要です。
予防歯科について

歯を失う原因であるむし歯と歯周病から歯の健康を守るためには、まずその原因について知り、対策をすることが大切です。
むし歯と歯周病、それぞれの原因と対策について解説します。
むし歯の発生原因とは?
むし歯は、口の中の細菌・糖分の摂取・歯の質など、いくつかの要因がからみ合って発生します。
歯垢(プラーク)を住みかとしている「むし歯菌」と口の中に入ってきた糖分がからみ合い、歯垢が取り除かれずに合わさったままで放置される歯のエナメル質を溶かし、とむし歯に発展する仕組みです。
むし歯の予防と対策について
むし歯の原因は歯垢(プラーク)に含まれたむし歯菌が酸をつくり、歯のエナメル質を溶かしてしまうことです。
そこでむし歯菌の住みかである歯垢をしっかり取り除くことができれば、確実に予防することができます。
毎日の歯みがきを欠かさずに、歯垢がたまりやすいところを重点的にみがくことが重要です。
また、むし歯は生活習慣も大きく影響します。
甘いものを摂取しすぎないようにしたり、ダラダラ食べを控えたりといった日常生活の改善も大切です。
歯垢が落としきれているかどうか、口腔内のすみずみをセルフチェックするには限界があります。
少なくとも年に1~2回は定期的に歯科医院で口腔内の状態をチェックしてもらったり、クリーニングやブラッシング指導を受けたりするなどして対策しましょう。
歯周病の原因とは?
初期の歯周病は痛みなどの自覚症状がほとんどないため、知らないうちに進行してしまい、気が付いた時には手遅れになっていたというケースも少なくありません。
口腔内だけに限らず全身の健康にも関係するため、早めに予防と治療を行うことが大切です。
歯周病は歯と歯ぐきの間に歯垢や歯石がたまり、その中にいる歯周病菌が歯ぐきの炎症を引き起こして発生します。
さらに生活習慣の悪化や免疫低下が加わると、口臭・歯ぐきの出血・腫れが続き、ついには歯が抜けてしまうので注意が必要です
歯周病発生の要因をまとめるのようになります。
| 細菌によるもの | 歯周病菌をかかえこむ歯垢 |
| 環境によるもの | 喫煙やストレス、不規則な生活などの生活習慣 |
| 老化や遺伝子的要因 | 老化や遺伝子などに加え、糖尿病や肥満、骨粗しょう症など |
歯周病の予防と対策について
歯周病は歯と歯ぐきの間にたまった歯垢の中にある歯周病菌が歯を支える組織を破壊し、歯根膜や歯槽骨を溶かすため、進行が進むと歯が抜けてしまいます。
そこで対策の基本は、歯周病菌の巣になる歯垢と歯石をしっかり取り除くことです。
歯周病は歯が抜けてしまうだけでなく、糖尿病や動脈硬化、狭心症や心筋梗塞といった身体のさまざまな病気と深く関わっていることもわかってきています。
歯周病予防は身体全体の健康にもつながるでしょう。
セルフケアで歯垢を取り除けても、歯石の除去や歯周ポケットに入り込んだ歯垢や歯石の除去は困難です。
入り込んだ歯垢や歯石の除去には、歯科医師や歯科衛生士による専門的なケアが必要になります。
歯周病対策として、年に1~2回の健診とともに定期的なクリーニングを受けるようにしましょう。
歯がなくなったときの治療法

歯を失ってしまった場合、欠損した箇所をそのままにしておくと全体の歯並びや噛み合わせに影響し、口腔内や身体全体の健康面においても良い状態とはいえなくなります。
そこで失った歯を補うための治療が必要です。
失った歯を補う3つの治療法について解説していきます。
入れ歯
歯を失った部分を義歯で補う入れ歯について解説します。
どんな治療法
入れ歯とは、失った歯の代わりに人工樹脂で連結して作られた人工の歯です。
健康な歯と歯ぐきに入れ歯を固定することにより、食べ物を噛む機能を回復させます。
欠損した場所により、入れ歯は1本からの作成が可能です。
主に3本以上歯を失ってしまった場合に適した治療法で、すべての歯が無い場合は「総入れ歯」、部分的に歯が無い場合は「部分入れ歯」を入れます。
入れ歯は「総入れ歯」も「部分入れ歯」も取り外しが可能です。
入れ歯のメリットとデメリットについても見ていきましょう。
入れ歯のメリット
- 3本以上歯を失ってしまった箇所でも治療が可能
- 取り外しができるので洗える
- バリエーションが多いため、症状に合わせた製作が可能
- 保険適用の入れ歯もあるため比較的安価で治療できる
入れ歯のデメリット
- 両隣の歯にかけた金具に汚れが溜まりやすいためむし歯や歯周病のリスクがある
- 金具をかけた部分に負担がかかるので両隣の歯の寿命を縮めるリスクがある
- 慣れるまで違和感があったり、食事や会話に支障がでたりする可能性がある
- 固定している金属により見た目を損なう恐れがある
ブリッジ
失った歯を補う「ブリッジ」という治療法について解説します。
どんな治療法
ブリッジとは、失った歯の両隣の歯を削って、失った歯と両隣の歯を連結させた被せものを装着する治療法です。
主に失った歯の本数が1~2本の場合に行われます。
入れ歯のように取り外しはできませんが、しっかり固定されているので安定感があると感じるでしょう。
ブリッジのメリットとデメリットは以下のとおりです。
ブリッジのメリット
- しっかり固定されているため、違和感が少なく、安定感がある
- 保険適用される場合があるため、比較的安価に治療できる
- インプラントに比べると治療期間が短くすむ
ブリッジのデメリット
- 被せもので固定するため、健康な両隣の歯を削ることになる
- 支えている健康な歯の寿命を縮めるリスクがある
- ブリッジと歯ぐきの間に汚れが溜まりやすいため、むし歯や歯周病のリスクが高い
インプラント
失った歯を補うインプラントという治療法について解説します。
どんな治療法
インプラントとは、失った歯の代わりに人工の歯の根っこ(チタン製)を埋めて、その上から人工の歯の被せものを装着する治療法です。
入れ歯やブリッジといった治療法と比べると、インプラントは天然の歯に一番近い構造の治療法といえます。
また、入れ歯やブリッジのように周りの健康な歯に負担をかけにくいため、おすすめの治療法です。
インプラントのメリットとデメリットも確認してみましょう。
インプラントのメリット
- 天然の歯とほぼ同じ構造のため、自然な見た目になる
- 歯が抜けた部分にのみに施術するため、周りの健康な歯に負担をかけなくて済む
- 天然の歯に近いため違和感も少なく、食事や会話にも影響が少ない
- 天然の歯とほぼ同じように噛むことができるので噛み合わせが安定する
- 顔の筋肉にも天然の歯とかわらない刺激を与えられる
インプラントのデメリット
- 手術を行う必要がある
- 骨が足りない場合、骨組織を再生する治療が必要
- インプラントができない場合がある
- 入れ歯やブリッジに比べて治療費が高くなる
できるならおすすめはインプラント

歯を失った場合の治療法について3つご紹介しましたが、可能であればおすすめの治療法はインプラントです。
インプラントは天然の歯に一番近い形で失った歯を補えて、周りの健康な歯に負担をかけません。
治療にあたっては、費用や時間が必要です。
しかし噛めない・空気が漏れるなどを防げるので、食事や会話といった日常生活に支障が出ません。
適切なケアを行うことで半永久的にインプラントを使っていくことができるでしょう。
インプラントの種類

現在、日本では20数種類のインプラントが販売されています。
タイプは大きく分けると、インプラント体とアタッチメントが一体化した「ワンピースタイプ」と、インプラント体にアタッチメントを連結するタイプの「ツーピースタイプ」の2タイプです。
インプラント体には、スクリュータイプとシリンダータイプの2タイプがあります。
多く採用されているのは、骨に固定されやすく、噛む力を周囲の骨に分散できるスクリュータイプです。
インプラントの術式には、大きく分けて、手術を1回だけ行う1回法と手術を2回に分けて行う2回法とがあります。
1回法と2回法の違いについて、簡単にまとめると以下のとおりです。
| 1回法 | インプラント体を埋める部分の粘膜を切開し、骨にドリルで穴をあけを埋め込みます。 骨の量が十分にあり、骨が硬い場合は1回法で問題ありません。 |
| 2回法 | インプラントを埋め込むまでは1回法と同じです。 インプラント体が骨と結合するまで3カ月~5カ月前後待ってから2回目の手術を行います。 骨の量が少なく、骨移植が必要な場合や、骨が軟らかい場合には2回法を行うのが一般的です。 |
インプラントを長持ちさせるために

種類によって多少の差異はあるものの、インプラントの残存率は、10年間で上あご、下あご共に約90%です。
しかし、インプラントは治療により失った歯を補ったら完了ではありません。
ずっと長持ちさせるためには、天然の歯と同様以上に日常のお手入れと観察が大切です。
装着後1年以内は、1カ月・3カ月・半年・1年と細かく診察兼メンテナンスを行います。
1年以降は特に問題がなければ年に1~2回の定期健診やメンテナンスを行うのが一般的です。
日常のセルフメンテナンスでは、歯ブラシに加え歯間ブラシやデンタルフロス等を使用して清掃を行います。
効果的に使用できるように、はじめは歯科衛生士からブラッシング指導を受けるのがおすすめです。
まずは歯を無くさないこと
今回は歯が無くなる原因と無くなった場合の治療法について解説してきました。
歯を失ってしまった場合でも、今回ご紹介した治療法により補うことができます。
まずは歯を失わないようにすることが大切なので、日常のお手入れをしっかり行っていきましょう。