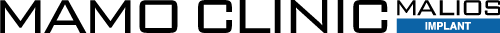お子さまの歯並び、ふとした瞬間に「これって大丈夫かな?」と気になり始めることはありませんか?前歯の生え方が少し斜めだったり、学校の歯科検診で指摘を受けたりと、最初は漠然とした不安でも、日々お子さまの成長を見る中で、本格的に歯列矯正を検討し始める保護者の方は少なくありません。
このコラムでは、そんな保護者の方々が抱える疑問や不安を解消できるよう、子どもの歯列矯正を始めるのに最適な時期、治療を始める前の準備、具体的な治療の流れ、そして気になる費用について、専門用語を使わずに分かりやすく解説します。お子さまの健やかな成長のために、ぜひ最後まで読み進めて、安心して歯列矯正に取り組むための第一歩を踏み出してください。
子どもの歯並びが気になる理由とは?
お子さまの前歯の生え方が気になったり、学校の歯科検診で歯並びについて指摘を受けたりして、お子さまの歯並びに疑問や不安を感じ始める保護者の方は少なくありません。歯並びは見た目だけでなく、お子さまの成長や健康に深く関わっています。このセクションでは、なぜ歯並びが気になるのか、その具体的なきっかけに触れながら、歯並びが悪い場合に起こりうる様々な問題や、その原因について詳しくご説明します。
歯並びが悪いと起こる問題
歯並びが整っていないことによる影響は、見た目の問題だけに留まりません。お子さまの心身の健康、そして将来の生活にまで影響を及ぼす可能性があります。ここでは、保護者の皆さまが矯正治療の必要性を客観的に理解できるよう、歯並びの悪さが引き起こす具体的な問題を3つの側面から掘り下げてご説明します。
噛み合わせの影響
歯並びの悪さは、まず「噛み合わせ」に大きな影響を与えます。食べ物を噛むという行為は、消化の第一歩であり、正しく噛めないと食べ物が十分に細かくなりません。その結果、消化器官に負担がかかり、消化不良や栄養吸収の効率低下につながる可能性があります。
また、一部の歯に過度な負担がかかることで、特定の歯がすり減ったり、欠けたりするリスクも高まります。さらに、顎の関節にも不均衡な力が加わるため、顎関節症(あごの関節の痛みや動きの制限)を引き起こす原因となることもあります。このような噛み合わせの問題を「不正咬合(ふせいごう)」と呼びます。
不正咬合には、出っ歯(上顎前突)、受け口(下顎前突)、開咬(奥歯を噛み合わせても前歯が開いている状態)、叢生(歯がでこぼこに生えている状態)など、様々な種類があります。これらの状態が長期にわたると、口腔全体の健康を損なうことにつながるため、早期の発見と対応が重要になります。
発音や話し方への影響
歯並びは、私たちが言葉を発する際の「発音」にも密接に関わっています。特に、前歯の隙間が大きい「すきっ歯」(空隙歯列)の場合、サ行の音が舌の先から漏れてしまい、不明瞭な発音になることがあります。また、受け口のお子さまの場合、タ行やナ行の音がこもりがちになったり、発音しにくくなったりすることがあります。
これは、歯並びが乱れていると、舌が正しい位置に収まらなかったり、スムーズに動かせなかったりするためです。舌は言葉の形成に重要な役割を担っており、歯と舌の位置関係が乱れると、発音の明瞭さが損なわれてしまいます。滑舌が悪い状態が続くと、お子さまがコミュニケーションに自信を持てなくなる可能性も考えられます。
お子さまが特定の音を苦手としていたり、話すことをためらったりする様子が見られる場合は、歯並びが影響している可能性も視野に入れることが大切です。
見た目のコンプレックス
お子さまの成長において、歯並びは見た目の印象に大きく影響し、それが心理面にまで及ぶことがあります。特に思春期に差し掛かると、自身の容姿に対する意識が高まるため、歯並びがコンプレックスとなってしまうお子さまも少なくありません。例えば、人前で口を開けて笑うことをためらったり、会話中に手で口元を隠す仕草が増えたりするような行動が見られることがあります。
こうした自己意識の変化は、お子さまの自己肯定感を低下させ、内向的になってしまうきっかけとなる可能性もあります。保護者の皆さまは、お子さまの言動だけでなく、普段の仕草や表情から心の変化に気づき、寄り添うことが非常に大切です。
適切な時期に歯並びを改善することで、お子さまはコンプレックスから解放され、自信を持って人前で笑えるようになります。見た目が整うことは、お子さまの心にも良い影響を与え、明るく前向きな気持ちで学校生活や社会生活を送るための大きな支えとなるでしょう。
歯並びが悪くなる原因
お子さまの歯並びが悪くなる原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合って生じることがほとんどです。遺伝的な体質だけでなく、日々の生活習慣や、成長過程での歯の生え変わり方も大きく影響します。ここでは、歯並びが悪くなる主な原因を「遺伝」「生活習慣」「歯の生え変わり」の3つのカテゴリに分けて詳しくご説明します。保護者の皆さまが「うちの子の場合はどれだろう?」と考えながら読み進めていただくことで、お子さまの歯並びの現状を理解する一助となれば幸いです。
遺伝的要因
歯並びは、親から子へと受け継がれる遺伝的な要素が関わることがあります。例えば、顎の骨の大きさや形、歯の大きさ、そして歯の数などが遺伝する可能性があるのです。これは、顔つきが親と子で似るのと同じように、骨格の特徴が遺伝することによるものです。
もし両親のどちらか、または両方が受け口(下顎前突)である場合、お子さまもその傾向を受け継ぎ、受け口になりやすい傾向があるといった具体例が挙げられます。遺伝が歯並びのすべてを決定するわけではありませんが、歯並びの問題を考える上で無視できない要素の一つと言えるでしょう。
生活習慣の影響
お子さまの歯並びには、無意識のうちに行っている癖や習慣が大きく影響することがあります。指しゃぶり、爪を噛む癖、唇を噛む癖、常に口が開いている口呼吸、そして舌で前歯を押す「舌突出癖」などがその代表例です。これらの癖は、歯や顎に継続的な力を加えることで、歯並びを徐々に乱してしまう可能性があります。
例えば、長期間の指しゃぶりは、上の前歯を前に押し出し、下の前歯を内側に倒してしまうことで「出っ歯」を引き起こす主な原因の一つとなります。また、口呼吸が続くと、舌の位置が本来よりも下がってしまい、上の顎が十分に発達せず、歯が並びきらない狭い顎になったり、出っ歯を悪化させたりすることもあります。舌突出癖がある場合は、下の前歯が前方に押し出され、歯と歯の間に隙間ができてしまう開咬につながることもあります。
保護者の皆さまは、お子さまの日常的な行動に注意を払い、もし気になる癖があれば、それが歯並びに悪影響を与えている可能性を考慮して、早めに改善を促すことが大切です。
乳歯の抜け方や永久歯の生え方
乳歯から永久歯への生え変わりのプロセスは、将来の歯並びにとって非常に重要です。この時期のトラブルが、その後の歯並びに大きな影響を与えることがあります。
例えば、虫歯などで乳歯が予定よりも早く抜けてしまうと、その空いたスペースに奥の歯がずれてきてしまうことがあります。すると、本来そのスペースに生えてくるはずの永久歯の場所が足りなくなり、永久歯が正しい位置に生えられず、でこぼこの歯並びになったり、横から生えてきたりする原因となることがあります。
逆に、乳歯がなかなか抜けずに残ってしまい、その乳歯の裏側から永久歯が生えてくる「二重歯列」になるケースもあります。このような場合も、永久歯が適切な位置に並ぶことが難しくなります。お子さまの歯の生え変わりは、個人差が大きいものですが、定期的な歯科検診を受けることで、この重要な時期の歯の成長を適切にチェックし、必要に応じて歯科医師に相談することが、将来の美しい歯並びへとつながるでしょう。
歯列矯正を始める最適な時期
お子さまの歯並びが気になり始めたとき、いつから矯正治療を始めれば良いのか、多くのお父さんやお母さんが悩まれるのではないでしょうか。実は、矯正治療には、顎の成長をコントロールしながら歯並びを整える「第一期治療」と、永久歯がすべて生えそろってから本格的に歯並びを整える「第二期治療」という二つの考え方があります。このセクションでは、特に「第一期治療」の開始時期に焦点を当てて、お子さまにとって最適なタイミングを見つけるための大切な情報をお伝えします。この情報が、お子さまの歯並びの未来を考える上で、具体的な一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
矯正開始時期の目安
お子さまの歯列矯正をいつから始めるべきかという問いには、明確な「何歳から」という答えがあるわけではありません。お子さま一人ひとりの成長のペースや、歯並びの状態によって最適なタイミングは異なります。しかし、顎の成長を活かせる時期を逃さないことは、治療をより効果的かつスムーズに進める上で非常に重要になります。
この時期に治療を始めることで、将来的に抜歯を避けられたり、第二期治療が必要になった場合でもその期間を短縮できたりする可能性が高まります。具体的な目安としては、乳歯から永久歯への生え変わりが進む「混合歯列期」が挙げられます。続く項目で、この時期がなぜ重要なのか、そしていつ頃が一般的な目安となるのかを詳しくご説明します。
乳歯から永久歯への移行期
乳歯と永久歯が混在する時期は「混合歯列期」と呼ばれ、歯列矯正、特に第一期治療を開始するのに非常に適していると言われています。この時期のお子さまの顎の骨はまだ柔らかく、成長の途中にあるため、矯正装置を使って顎の成長を良い方向に誘導しやすいという大きなメリットがあります。
例えば、顎の成長が足りないために永久歯がきれいに並ぶスペースが不足している場合でも、この時期に顎を広げるような処置を行うことで、将来的に永久歯を抜かずに済む可能性を高めることができます。また、永久歯が生えそろう前に顎のバランスを整えておくことで、本格的な第二期治療が必要になったとしても、治療期間が短くなったり、よりシンプルな治療で済んだりすることも期待できます。
小学校低学年から中学年のタイミング
具体的な年齢の目安としては、小学校の低学年から中学年にあたる6歳から10歳頃が、矯正治療を検討する一つの良いタイミングとされています。この時期は、永久歯である前歯や、一番奥に生えてくる6歳臼歯(第一大臼歯)が生えそろう頃にあたり、噛み合わせの土台が作られ始めるからです。
この大切な時期に、すでに受け口や出っ歯といった噛み合わせの問題が見られる場合や、永久歯が生えるスペースが足りないといった症状がはっきりと現れてくることがあります。また、学校の歯科検診で歯並びや噛み合わせについて指摘を受けることが多くなるのも、この時期の特徴です。そのため、もしお子さまがこの年齢に差し掛かり、歯並びが気になり始めたら、一度歯科医院で相談してみることをおすすめします。
個人差を考慮した診断の重要性
これまでお伝えした目安は、あくまで一般的な傾向です。お子さまの矯正治療において最も大切なのは、一人ひとりの成長のスピードや、顎の骨の状態、歯の生え変わりの状況が大きく異なるという「個人差」を理解することです。同じ年齢のお子さまでも、骨格の成長度合いや歯の発育状況は本当に様々です。
「うちの子はまだ早いかもしれない」「もう手遅れになってしまっていたらどうしよう」とご自身で判断される前に、まずは矯正治療を専門とする歯科医師に相談することが何よりも重要です。専門家による正確な診断を受けることで、お子さまに最適な治療開始時期や方法を見つけることができます。これが、後悔のない治療選択のための最も確実な方法と言えるでしょう。
矯正を始める前に確認すべきこと
お子さまの歯列矯正を検討し始めると、「どこから手をつければいいのだろう」「どんな準備が必要なのだろう」と迷われるかもしれません。矯正治療は、時間も費用もかかる大きな決断です。だからこそ、歯科医院に相談に行く前に、ご家庭でいくつか確認し、準備しておくべきことがあります。
このセクションでは、矯正治療をスムーズに始めるために保護者の方が事前に知っておきたいこと、そして実際にできる具体的な準備についてリストアップ形式でご紹介します。これらの準備をしておくことで、より安心して治療のステップへ進むことができるでしょう。
歯科医師による初期診断
矯正治療の第一歩として、歯科医師による初期診断を受けることは非常に重要です。この初回カウンセリングでは、まずお子さまのお口の状態を診察し、歯並びや噛み合わせに関するお悩みを詳しく聞いてもらえます。その後、治療計画を立てるために必要な精密検査が行われることが一般的です。精密検査では、お口の中や顔全体のレントゲン撮影、歯型を採るための印象採得、口の中や顔の写真撮影などが行われます。
これらの検査結果をもとに、歯科医師からお子さまの歯並びの状態や、考えられる治療の選択肢、おおよその治療期間、そして費用について具体的な説明を受けることができます。この機会に、「治療のメリットとデメリットは?」「痛みの程度はどれくらいですか?」「もし途中で治療をやめたくなったらどうなりますか?」など、気になることはどんな小さなことでも質問し、疑問や不安をすべて解消しておくことが、納得して治療を始めるための大切な準備となります。
家族のスケジュール調整
矯正治療が始まると、月に1回程度の定期的な通院が必要になることがほとんどです。お子さまの治療をスムーズに進めるためには、この通院スケジュールを家族のライフスタイルにどう組み込むか、事前にシミュレーションしておくことが重要になります。
共働きのご家庭の場合、どちらが送迎を担当するか、お子さまの習い事や学校行事との兼ね合いはどうするかなど、あらかじめ話し合っておくことで、治療中の負担を減らすことができます。また、学校帰りにも立ち寄れる場所にある歯科医院を選ぶ、オンライン予約システムを活用するなど、通院の利便性も考慮に入れると良いでしょう。
子どもの心理的準備
矯正治療は長期間にわたることが多いため、お子さま自身の協力が不可欠です。そのため、治療を始める前には、お子さまの心理的な準備をしっかり整えてあげることが非常に大切になります。まずは、なぜ矯正が必要なのかを、お子さまの年齢に合わせてわかりやすく説明してあげましょう。「歯がきれいになると、もっと素敵な笑顔になるよ」「しっかり噛めるようになると、もっと美味しくごはんが食べられるようになります」といったように、治療によって得られるポジティブな未来を具体的に伝えてあげると良いでしょう。
また、治療中に装置の装着による違和感や、歯が動くことによる軽い痛みを感じることがあるかもしれません。そのような可能性についても正直に伝え、「少し痛いときもあるけれど、これは歯が頑張って動いている証拠だよ。乗り越えれば、素晴らしい結果が待っているから一緒に頑張ろうね」といった前向きな言葉で励ましてあげましょう。不安な気持ちに寄り添い、お子さまが「がんばってみよう」と思えるような声かけを心がけることが、治療の成功へとつながります。
矯正治療を始めるための準備ポイント
子どもの歯並びを整えるための矯正治療を検討されている保護者の方にとって、実際にどのような装置を使うのか、治療期間はどれくらいか、痛みは伴うのかといった具体的な情報は、治療への一歩を踏み出す上で非常に重要になることでしょう。このセクションでは、矯正治療を始めるにあたって知っておきたい実践的な情報を詳しく解説します。ここからの情報が、お子さんの治療開始後の生活を具体的にイメージし、安心して治療に臨むための一助となれば幸いです。
矯正器具の種類と選び方
子どもの矯正治療では、さまざまな種類の装置が使われます。それぞれの装置には、見た目、費用、治療できる歯並びの種類、そしてお子さまの協力がどのくらい必要かといった点で違いがあります。どの装置が一番合っているかは、お子さまの歯並びの状態や成長段階によって一人ひとり異なりますので、最終的には歯科医師とよく相談して決めることが大切です。
例えば、目立ちにくい装置を選びたい、食事のときに外せるものがいい、費用を抑えたいなど、保護者の方やご本人のお気持ちによって選択肢は変わってきます。ここでご紹介するそれぞれの装置の特徴を理解して、歯科医師との相談に役立ててみてくださいね。
固定式矯正器具(ブラケット)
「ワイヤー矯正」としてよく知られているのが、この固定式矯正器具(ブラケット)です。歯の表面に小さな「ブラケット」という装置を一つひとつ接着し、そこに細いワイヤーを通して歯を少しずつ動かしていく仕組みです。この方法は、幅広い歯並びの乱れに対応でき、非常に高い矯正力を持っています。
ブラケットは一度つけたら取り外しができないため、お子さまが装置を外してしまう心配がなく、計画通りに治療が進みやすいという大きなメリットがあります。一方で、金属製のブラケットは目立ちやすく、歯磨きがしにくくなるというデメリットもあります。最近では、透明なセラミック製のブラケットなど、目立ちにくい素材も選べるようになっていますので、見た目が気になる場合は相談してみるのも良いでしょう。
取り外し可能な矯正器具(マウスピース)
マウスピース矯正は、透明なプラスチック製のマウスピースを、段階的に新しいものに交換していくことで歯を動かす治療法です。この装置の最大のメリットは、透明なのでつけていても目立ちにくく、食事や歯磨きの際には自分で取り外せるため、衛生的であるという点です。
ただし、マウスピース矯正は、お子さま自身の協力が非常に重要になります。治療計画通りに歯を動かすためには、1日に20時間以上など、歯科医師から指示された装着時間をきちんと守る必要があります。装着時間が短いと、計画通りに歯が動かず、治療期間が延びてしまったり、再治療が必要になったりする可能性もありますので、お子さまがきちんと装着できるかどうかが成功のカギとなります。また、全ての歯並びの問題に対応できるわけではないため、適用できる症例には限りがある場合もあります。
特殊な矯正器具(ヘッドギアなど)
第一期治療では、成長期のお子さまの顎の骨の成長をうまく利用するために、特殊な矯正器具が使われることがあります。例えば、「拡大床(かくだいしょう)」は、上顎の幅を広げて永久歯が生えるスペースを確保する目的で使われます。また、「ヘッドギア」は、出っ歯の治療などで上顎の成長を抑えたり、奥歯を後ろに動かしたりするために、頭部から力をかける装置です。受け口の治療では、「上顎前方牽引装置」という顎を前に引っ張る装置が使われることもあります。
これらの特殊な装置は、おもに自宅で夜間など、お子さまが寝ている時間帯に装着することが多いです。そのため、学校生活への影響は比較的少ないですが、毎日忘れずに決められた時間装着することが重要になります。お子さまの協力が必要な装置ですので、歯科医師から使い方や注意点をしっかり聞き、親子で取り組む姿勢が大切になります。
矯正治療前に知っておきたいこと
子どもの歯並びの矯正治療を考え始める保護者の方にとって、治療にかかる期間や、お子さんが感じるであろう痛み、日常生活での食事の制限など、様々な不安や疑問があるかと思います。ここでは、そうした保護者の方が抱きがちな不安に焦点を当てて、具体的な情報をお伝えしていきます。治療中の生活がどのようなものになるのかを具体的にイメージできるよう、分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
これらの情報を事前に知っておくことで、治療に対する心の準備ができ、お子さんと一緒に治療を乗り越えるための具体的な対策を立てることができます。治療が始まってから戸惑うことがないよう、治療期間の目安や痛みの対処法、食事の注意点などを詳しく見ていきましょう。
治療期間の目安
子どもの歯列矯正にかかる期間は、お子さんの歯並びの状態や治療方法によって様々ですが、一般的な目安をお伝えします。子どもの矯正治療は大きく「第一期治療」と「第二期治療」に分かれることが多く、それぞれに期間がかかります。
第一期治療は、主に顎の成長をコントロールして、永久歯がきれいに生えそろうための土台作りをする期間で、1年から3年程度が一般的です。一方、永久歯が生えそろった後に行う第二期治療は、歯の一つひとつの位置を細かく調整していく期間で、こちらは1年半から3年程度の期間を要します。治療装置を外した後も、歯が元の位置に戻ろうとする「後戻り」を防ぐために、歯並びを安定させるための「保定期間」が必要になります。保定期間は数年間続くこともあります。
ただし、これらの期間はあくまで目安です。お子さんの骨格の成長スピードや、治療への協力度、歯の動き方によって、治療期間は長くなったり短くなったりと大きく変動することがあります。そのため、具体的な治療期間については、歯科医師による精密な診断と治療計画の説明をしっかりと聞くことが大切です。
痛みや違和感への対処法
矯正治療を始めるにあたり、保護者の方が最も心配されることの一つに「痛み」があります。装置を初めて装着した時や、月に一度の調整を行った後の数日間は、歯が動くことによる圧迫感や鈍い痛みを感じることが多いです。痛みには個人差がありますが、「歯が浮いた感じがする」「食べ物を噛むと響く」といった種類の痛みを訴えるお子さんもいます。
このような痛みや違和感は、歯が移動する際に起こる自然な反応であり、通常は2、3日から1週間程度で落ち着くことがほとんどです。対処法としては、痛みが強い間は、おかゆやうどん、ゼリーなど、柔らかくて噛まなくても食べられる食事を用意してあげると良いでしょう。もし痛みが続くようであれば、我慢せずに歯科医師に相談してください。必要に応じて、市販の鎮痛剤の服用を勧められる場合もあります。
また、装置が舌や頬の内側に当たって口内炎ができてしまうこともあります。その場合は、歯科医院で渡される「矯正用ワックス」を装置の尖った部分に付けて、粘膜を保護してあげると痛みが和らぎます。矯正治療中の痛みや違和感は一時的なものですので、過度に心配せず、適切な対処を心がけることで乗り越えることができます。
矯正中の食事制限
矯正治療中は、装置の破損や脱離を防ぎ、また治療効果を最大限に引き出すために、食事にいくつかの注意点があります。特に、歯に固定するタイプの矯正装置(ブラケットやワイヤー)を使用している場合は、避けるべき食べ物があります。
具体的には、硬い食べ物(せんべい、氷、ナッツ、フランスパンの硬い部分など)は装置を壊す原因になることがあります。また、粘着性の高い食べ物(キャラメル、チューインガム、餅など)は装置に絡みつきやすく、外れてしまう可能性があるので注意が必要です。さらに、繊維質の多い野菜(葉物野菜のそのままのもの、トウモロコシなど)や、骨付き肉、リンゴの丸かじりなどは、装置の間に挟まりやすかったり、無理な力がかかったりするため、避けるか、調理方法を工夫する必要があります。
しかし、食べられないものがたくさんあるわけではありません。硬い食べ物でも小さく切ったり、柔らかく煮込んだりすることで、ほとんどのものを楽しむことができます。例えば、リンゴであれば薄切りにする、肉は小さく切ってから食べる、など工夫次第で食事の楽しみが大きく損なわれることはありません。取り外し可能なマウスピース型矯正装置を使用している場合は、食事の際に装置を外すことができるため、食事制限はほとんどないというメリットもあります。何が食べられるか、どのように工夫すれば良いかについては、歯科医院で具体的なアドバイスを受けることができますので、積極的に相談してください。
矯正治療をスムーズに進めるための準備
矯正治療は、数ヶ月から数年にわたる長い期間を要するものです。この長い道のりを、お子さんと保護者の方で協力し、気持ちよく乗り越えていくためには、治療開始前の準備がとても大切になります。お子さんのモチベーションを維持しながら、スムーズに治療を進めるための保護者の方の関わり方について、具体的なポイントをご紹介します。
治療中に起こりうる痛みや食事制限、歯磨きの大変さなど、お子さんが直面するであろう課題を事前に理解し、適切なサポートをすることで、お子さんは安心して治療に取り組むことができるでしょう。保護者の方が積極的に関わることで、お子さんは「一人で頑張っているわけではない」という安心感を得られ、治療への意欲を保ちやすくなります。
子どもへの説明と理解促進
矯正治療を始めるにあたって、お子さん自身が治療の必要性を理解し、納得していることは非常に重要です。なぜ歯並びを治すのか、治療によってどのような良いことがあるのかを、お子さんの年齢や理解度に合わせて具体的に説明してあげてください。「歯がきれいになると、もっと素敵な笑顔になれるよ」「しっかり噛めるようになると、もっとごはんが美味しくなるよ」といった前向きな言葉で、治療のメリットを伝えてみましょう。
歯科医院で、歯科医師がお子さんにも直接治療内容を説明する機会を設けてもらうのも良い方法です。専門家からの説明は、お子さんにとっても説得力があるでしょう。また、もし周りに矯正治療を経験した年上のお子さんがいれば、その子の体験談を聞かせてあげるのも、お子さんの不安を和らげ、前向きな気持ちを引き出すきっかけになります。お子さんを「治療を受ける当事者」として尊重し、決して一方的に治療を進めるのではなく、一緒に頑張るパートナーとして接してあげることが大切です。
矯正器具の扱い方を教える
矯正治療では、お子さん自身が矯正器具を正しく扱い、ケアすることが求められます。取り外し可能なマウスピース型矯正装置の場合であれば、正しい着脱方法や、毎日の洗浄方法をお子さん自身が習得することが重要です。また、固定式のワイヤー矯正の場合でも、装置周辺の歯磨きの仕方や、もしワイヤーが外れてしまった場合の初期対応など、お子さん自身が基本的な対応を理解しておく必要があります。
歯科医院で歯科衛生士から指導を受ける際には、保護者の方も同席して一緒に学び、家で実践できるようにサポートしてあげてください。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、毎日繰り返すことでお子さんは徐々に慣れていきます。自分の使っている装置を自分で管理する責任感を持たせることは、治療への主体的な参加を促し、将来の自立にもつながるでしょう。
定期的な歯科通院のスケジュール管理
矯正治療は、装置の調整や口腔内のチェックのために、月に1回程度の定期的な通院が必要になります。この定期通院をきちんと守ることは、治療計画通りに歯が動き、治療がスムーズに進むために欠かせません。ワイヤーの調整や交換、装置の微調整、虫歯や歯肉炎のチェックなど、通院ごとに様々な処置が行われます。
共働きのご家庭や、お子さんの習い事などとの兼ね合いで、通院スケジュールを管理するのは大変だと感じるかもしれません。カレンダーアプリの共有機能を使ったり、診察券を家族全員が見やすい場所に保管したりするなど、予約を忘れないための工夫を取り入れてみましょう。歯科医院によっては、土日診療を行っていたり、学校帰りでも立ち寄れる場所に位置していたりするところもありますので、通いやすさも考慮して医院を選ぶと、保護者の方の負担を軽減できるでしょう。
矯正治療の流れと注意点
子どもの歯列矯正を検討されている保護者の方にとって、実際に治療がどのように進んでいくのかは大きな関心事ではないでしょうか。このセクションでは、初めて歯科医院を訪れる段階から、治療が完了し、その後も良い状態を維持していくためのフォローアップまで、矯正治療の一連の流れを時系列に沿って詳しくご説明します。治療のステップを具体的に把握することで、これから何が起こるのかという漠然とした不安を解消し、安心して治療に臨んでいただけるようサポートいたします。
初診から治療開始までの流れ
このセクションでは、初めて歯科医院を訪れてから、実際に矯正装置を装着するまでの具体的な流れをステップ・バイ・ステップでご紹介します。このプロセスを事前に知ることで、お子さんの歯並びについてお悩みの保護者の方が、安心して治療のスタートラインに立てるようになります。
矯正治療は一度始めると、数年単位の長い期間を要するものです。そのため、治療が始まる前の準備期間で、歯科医師とのコミュニケーションを密にとり、疑問や不安を解消しておくことが大切です。ここで解説する内容を参考に、お子さんと一緒に治療への理解を深めていきましょう。
初回相談と診断
初めて矯正歯科を訪れると、まずはカウンセリングが行われます。ここでは、お子さんの歯並びで気になることや、いつ頃から気になっているのかなど、詳しくお話しいただく時間があります。歯科医師が直接お子さんの口の中の状態を診察する視診も行われ、現在の歯並びや噛み合わせの状態を確認します。
その上で、より詳しい治療計画を立てるために、精密検査を行います。レントゲン撮影で顎の骨の状態や永久歯の有無・位置を確認したり、歯型を採って歯の大きさや並び方を立体的に把握したりします。また、顔や口の中の写真を撮影し、治療前後の変化を記録するためにも使われます。これらの検査結果をもとに、お子さん一人ひとりに合った治療計画を立てていきます。
この初回相談の段階で、治療に関する疑問や不安はすべて歯科医師に伝えてください。「痛みはどのくらいありますか」「学校生活に影響はありませんか」など、どんな些細なことでも構いません。また、複数の歯科医院でセカンドオピニオンを聞くことも、納得して治療を始めるための有効な選択肢です。納得のいく治療を選択するためにも、気になることは積極的に質問しましょう。
矯正計画の立案
精密検査の結果が出たら、それを基に歯科医師からお子さんのための具体的な矯正治療計画が提示されます。この計画には、お子さんの歯並びの現状診断から始まり、治療によってどのような状態を目指すのかという目標が明確に示されます。
また、具体的にどのような矯正装置を使うのか、治療にかかるおおよその期間、そして治療費の総額についても詳しく説明があります。場合によっては、永久歯を抜歯する必要があるかどうかの説明もこの段階で行われます。保護者の方とお子さんが、提示された治療計画の内容を十分に理解し、納得した上で、治療を開始することに同意する旨の同意書にサインするプロセスがとても大切です。
この計画に沿って治療が進んでいきますので、不明な点や不安な点は遠慮なく質問し、すべてをクリアにしてから治療を開始するようにしましょう。お子さんの将来に関わる大切な選択ですので、家族みんなでよく話し合い、前向きな気持ちで臨んでください。
器具の装着と調整
治療計画に合意したら、いよいよ矯正装置を装着する日を迎えます。装置を装着する前には、まずお子さんの歯の表面をきれいにクリーニングします。これは、装置をしっかりと接着するためと、虫歯のリスクを減らすために非常に大切な工程です。
固定式のブラケット装置の場合、歯の表面に小さなブラケットを一つひとつ丁寧に接着し、そこにワイヤーを通していきます。マウスピース矯正の場合には、マウスピースの正しい装着方法や取り外す際の注意点について、歯科衛生士から詳しい指導があります。どちらの装置も、最初は慣れないかもしれませんが、すぐに慣れることができますので安心してください。
装置を装着した後は、今後の注意点について改めて説明があります。例えば、毎日の歯磨きの仕方や、装置を守るために避けるべき食べ物、そして次回の予約日などです。保護者の方とお子さんが、矯正治療という新しい生活をスムーズにスタートできるよう、歯科医院がしっかりとサポートしてくれますので、心配なことはその場で確認し、理解を深めていきましょう。
治療中に気をつけるべきこと
矯正治療は、数ヶ月から数年にわたる長い期間で行われるため、その間にはさまざまなことに気をつける必要があります。治療を計画通りに、そして安全に進めるためには、保護者の方とお子さんで協力して日々の生活で注意すべき点を理解し、実践していくことが大切です。ここでは、治療中に起こりがちなトラブルを未然に防ぎ、快適に過ごすための具体的なアドバイスをご紹介します。
例えば、矯正装置に食べ物が詰まりやすくなるため、これまで以上に丁寧な歯磨きが必要になります。また、装置が外れたり壊れたりすることのないよう、食事の内容やスポーツ時の注意も欠かせません。これらの点に気をつけることで、治療中の不快感を減らし、最終的に美しい歯並びへと導くことができます。
器具の破損を防ぐ方法
矯正装置は精密に作られていますが、日常生活での使い方によっては破損してしまうことがあります。特に固定式のブラケット装置は、硬いものを噛んだり、粘着性の高いものを食べたりすることで、外れてしまう可能性があるので注意が必要です。例えば、おせんべいやナッツなどの硬い食べ物、キャラメルやガムなどの粘着性のある食べ物は、装置に大きな負担をかけるため、できるだけ避けるようにしましょう。
また、お子さんがスポーツをする際には、口元に衝撃が加わることで装置が破損したり、口の中を傷つけたりするリスクがあります。サッカーやバスケットボールなど、接触の多いスポーツをする場合は、マウスガードを装着することをおすすめします。万が一、装置が外れてしまったり、ワイヤーの先が飛び出して口の中に刺さったりした場合は、自己判断で無理に触らず、速やかに歯科医院に連絡してください。応急処置として、矯正用ワックスを使って飛び出た部分を保護することで、口の中の痛みや傷つきを防ぐことができます。
歯磨きや口腔ケアの徹底
矯正治療中は、装置の周りに食べかすが挟まったり、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなったりするため、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。そのため、普段以上に丁寧な歯磨きと口腔ケアが不可欠です。通常の歯ブラシだけでなく、タフトブラシと呼ばれる先の細いブラシや、歯間ブラシ、デンタルフロスなどを活用することで、装置の隙間や歯と歯の間など、磨きにくい部分もきれいにすることができます。
歯科医院では、矯正中の正しい歯磨きの方法や、清掃用具の選び方について指導がありますので、積極的に学んで家庭で実践しましょう。毎食後、時間をかけて丁寧に歯磨きを行う習慣を身につけることが、治療期間中の口腔内を健康に保つ上で非常に重要です。美しい歯並びを手に入れるだけでなく、虫歯や歯周病のない健康な歯を維持するためにも、日々の徹底したケアを心がけてください。
子どものモチベーション維持
長期間にわたる矯正治療は、お子さんにとって精神的な負担になることもあります。特に、装置の違和感や痛み、食事の制限、見た目への抵抗などから、途中でモチベーションが下がってしまうこともあるかもしれません。そのような時に、保護者の方のサポートが大きな力となります。まずは、お子さんの気持ちに寄り添い、「頑張っているね」「少しずつ歯が動いてきれいになってきたね」といったポジティブな声かけを続けることが大切です。
また、定期的に歯並びの変化を一緒に確認し、治療のゴールが近づいていることを実感させてあげるのも良い方法です。例えば、治療開始時の写真と現在の写真を比較して見せたり、歯がきれいになったらしたいこと(例えば、「もっと自信を持って笑えるようになる」「好きな食べ物がもっと美味しくなる」など)を具体的に話し合ったりするのも効果的です。調整日で頑張った日には、お子さんの好きなものを用意してあげるなど、小さなご褒美を設定することも、やる気を維持する助けになります。保護者の方が一番の理解者として、前向きにサポートし続けることが、お子さんが治療を最後までやり遂げるための鍵となるでしょう。
治療後のフォローアップ
矯正装置が外れたら、治療は終わりだと感じるかもしれません。しかし、実はその後のフォローアップが、美しい歯並びを一生涯保つために非常に大切なのです。歯は、矯正装置によって動かされた後も、元の位置に戻ろうとする「後戻り」を起こしやすい状態にあります。そのため、この後戻りを防ぎ、歯並びを安定させるためのステップが必要になります。ここでは、矯正治療で得られた成果をしっかりと維持していくために、保護者の方に知っておいていただきたい重要なポイントを解説していきます。
せっかく頑張った治療が無駄にならないよう、治療後のケアも丁寧に進めていくことが、お子さまの将来の健康と自信につながります。
保定装置の使用
矯正装置が外れた後、歯科医師から「保定装置(リテーナー)」の装着を指示されます。これは、歯が新しい位置に安定するまで、その位置を保つための非常に重要な装置です。矯正治療で歯を動かすことは、例えるなら、骨の中に埋まっている歯の根っこごと移動させる大工事のようなものです。装置を外した直後の歯の周囲の骨や歯茎は、まだ新しい位置に慣れていないため、何もせずにいると元の位置に戻ろうとします。
リテーナーは、動かした歯を新しい位置で固定し、骨や歯茎が安定するのを助ける「ギプス」のような役割を果たします。取り外しができるタイプや、歯の裏側に固定するタイプなど様々な種類があります。歯科医師の指示通りに、決められた時間、毎日きちんと装着することが何よりも重要です。ここで手を抜いてしまうと、せっかくの時間と費用をかけた治療が水の泡になり、再び歯並びが乱れてしまう「後戻り」を引き起こす可能性が高まります。
定期的なチェックアップ
保定装置を装着している期間も、定期的に歯科医院でのチェックアップが必要です。これは、歯並びがきちんと安定しているか、リテーナーが正しく機能しているか、そして虫歯や歯周病など、お口全体の健康状態に問題がないかを確認するためです。通常、数ヶ月に一度程度の通院が目安となります。
定期的なチェックアップに通うことで、万が一、後戻りの兆候が見られた場合でも、早期に発見して対処することができます。また、お子さまの成長に合わせて、かみ合わせの変化や親知らずの生え方なども確認してもらえるため、長期的な視点でお口の健康を守ることにつながります。自己判断で通院をやめてしまわず、歯科医師の指示に従って最後まで通い続けることが大切です。
長期的な歯並びの維持方法
保定期間が終了した後も、美しい歯並びと健康な口腔環境を維持していくためには、日々のセルフケアとプロフェッショナルケアを継続していくことが不可欠です。矯正治療によって歯並びが整ったことで、歯磨きがしやすくなり、虫歯や歯周病のリスクは大幅に減少します。しかし、油断は禁物です。
毎日の丁寧なブラッシングはもちろんのこと、歯科医院での定期的な歯科検診とプロフェッショナルクリーニングを習慣にすることをおすすめします。これにより、磨き残しによる歯垢や歯石の蓄積を防ぎ、健康な歯と歯茎を維持することができます。矯正治療は、単に見た目をきれいにするだけでなく、お子さまが生涯にわたってご自身の歯で健康に過ごしていくための「最高の予防歯科」なのです。治療で得られた成果を大切にし、お口の健康に意識を向けて生活する習慣を身につけさせてあげましょう。
歯列矯正にかかる費用と保護者の負担
お子さんの歯列矯正を検討する上で、多くの保護者の方が最も気になる点の一つが費用ではないでしょうか。歯列矯正は基本的に自由診療となるため、保険適用となる病気や症状の場合を除いては、費用が高額になる傾向があります。このセクションでは、矯正治療にかかる費用の内訳や、少しでも保護者の方の負担を軽減するための具体的な方法について詳しくご説明していきます。
矯正治療の費用の目安
子どもの歯列矯正にかかる費用は、保護者の方にとって非常に気になる点かと思います。治療の総額は、お子さんの歯並びの状態、選ぶ治療方法、そして歯科医院によって大きく異なります。目安としては、永久歯が生えそろう前の段階で行う「第一期治療」で30万円から50万円程度、永久歯が生えそろってから行う「第二期治療」では70万円から120万円程度が一般的です。
この金額はあくまで目安であり、治療法や使用する装置の種類によって変動することを理解しておくことが大切です。費用だけで治療の質を判断せず、提示された金額に何が含まれているのか、具体的に確認することが重要になります。治療費の内訳をしっかりと把握し、納得のいく形で治療を進められるよう、次の項目で詳しく見ていきましょう。
初期診断費用
矯正治療を始めるにあたって、まず必要となるのが初期診断にかかる費用です。これは、お子さんの歯並びや顎の状態を詳しく調べるために行われるカウンセリングや精密検査にかかる費用を指します。具体的には、問診、口腔内の検査、レントゲン撮影、歯型の採取、顔や口の中の写真撮影などが含まれます。
初期診断費用は、数千円から数万円程度が目安です。歯科医院によっては、この初期診断費用が治療費の総額に含まれている場合もあれば、別途支払いが必要な場合もあります。複数の歯科医院で相談し、治療方針や費用を比較検討する際には、それぞれの医院で相談料や検査料が発生する可能性がある点も考慮しておくと良いでしょう。
矯正器具の費用
矯正治療の費用の中で最も大きな割合を占めるのが、実際に歯を動かすために使用する矯正器具の費用です。この費用は、選ぶ装置の種類によって大きく変動します。例えば、一般的なメタルブラケット(金属製の装置)、目立ちにくいセラミックブラケット、そして透明で取り外しが可能なマウスピース型矯正装置などがあります。
一般的に、見た目の目立ちにくさや利便性が高い装置ほど費用は高くなる傾向があります。お子さんの歯並びの状態や、治療に対する協力度、そして保護者の方の予算などを考慮しながら、歯科医師とよく相談して最適な装置を選ぶことが大切です。
定期調整費用
矯正治療期間中は、月に1回程度のペースで歯科医院に通い、装置の調整や歯の動きのチェックを行います。この際に発生するのが定期調整費用で、1回あたり3,000円から1万円程度が目安です。ワイヤーの交換や調整、口腔内の清掃や異常がないかの確認などが行われます。
矯正治療の料金体系には、治療開始から終了までの費用がすべて含まれる「トータルフィー制度」と、治療費と別に毎回の調整費用が必要な制度があります。契約前にどちらの料金体系を採用しているのか、また、何が含まれているのかをしっかりと確認し、ご自身の支払い計画に無理がないかを確認することが重要です。
費用を抑えるための工夫
子どもの歯列矯正は、成長段階を考慮した治療が必要になるため、費用が高額になりやすい傾向があります。しかし、経済的な負担が大きいからといって、大切な歯の健康を諦める必要はありません。費用負担を少しでも抑えるための方法や、利用できる制度がありますので、それぞれの家庭に合った選択肢を検討してみましょう。治療を始める前に、これらの工夫を知っておくことで、より安心して治療計画を立てることができます。
具体的な費用の抑え方を知ることで、保護者の皆様が抱える経済的な不安を少しでも軽減し、お子様にとって最適な歯列矯正を実現できるよう、さまざまな視点から情報を提供いたします。
保険適用の可能性
歯列矯正は、見た目を整える目的が主であるため、原則として保険が適用されない自由診療です。しかし、一部の特殊な症例では保険が適用されるケースもあります。たとえば、「顎変形症」と診断され、外科手術を伴う矯正治療が必要な場合や、厚生労働大臣が定める特定の先天性疾患(例:唇顎口蓋裂など)が原因で噛み合わせに異常がある場合は、保険診療の対象となります。
一般的な乱れた歯並びを治す目的の矯正治療は保険適用外であることがほとんどですが、ご自身のお子様が上記のようなケースに該当するかどうかは、まずは歯科医師に相談してみることをおすすめします。また、矯正治療は医療費控除の対象となる可能性が高いです。医療費控除は、世帯全体の年間医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担が軽減される制度ですので、ぜひご確認ください。
分割払いの利用
歯列矯正の費用は、数十万円から百万円を超えることもあり、一度に全額を支払うことが難しい場合もあるかと思います。そのような場合でも、多くの歯科医院では、患者さんの経済的な負担を軽減するために様々な支払い方法を用意しています。
例えば、歯科医院が提携しているデンタルローンを利用したり、歯科医院独自の分割払いの制度を利用したりすることで、高額な費用を月々の支払いに平準化できます。金利の有無や支払い回数、手数料などは歯科医院やローン会社によって異なりますので、契約前にしっかりと確認し、ご自身の家計状況に無理のない支払い計画を立てることが大切です。
歯科医院の選び方
矯正治療の費用は、歯科医院によって設定が異なるため、複数の歯科医院でカウンセリングを受け、治療方針や費用の見積もりを比較検討することは非常に重要です。しかし、費用が安いという理由だけで歯科医院を選ぶのは避けた方が良いでしょう。治療内容や使用する装置、医師の経験や実績によって費用は変わるため、単純な価格比較だけでは判断できません。
医師との相性、治療方針への納得感、そして無理なく通院を続けられる立地であるかなど、費用以外の要素も総合的に判断することが、最終的に満足のいく治療結果へとつながります。信頼できる歯科医師を見つけ、お子様にとって最良の治療環境を選ぶことが、治療成功への第一歩となります。
矯正治療中の家庭でのサポート
子どもの歯列矯正は、歯科医院での治療だけでなく、ご家庭での日々のサポートが成功の鍵を握っています。お子さまが治療をスムーズに進め、きれいな歯並びを手に入れるためには、保護者の方の理解と協力が不可欠です。特に「食事」「口腔ケア」「精神的な支え」の3つの側面から、保護者の方が具体的にどのようなサポートをすれば良いのかをご紹介します。
治療期間は長くなることも多いため、お子さまが治療に対して前向きな気持ちを保てるように、ご家庭でのサポートは非常に大切です。日々の生活の中で少しの工夫をすることで、お子さまの負担を減らし、治療効果を高めることができるでしょう。
子どもの食事管理
矯正装置を付けたばかりの頃や、調整のために歯科医院に行った後は、歯が動く痛みや違和感でお子さまが食事を摂りにくくなることがあります。このような時期には、無理なく食べられるやわらかいメニューを用意してあげましょう。おかゆ、スープ、ヨーグルト、プリン、ゼリーなどは、痛みがある時でも比較的食べやすい食品です。
また、固定式の矯正装置を使用している場合は、硬いもの(おせんべいやナッツ類)、粘着性の高いもの(キャラメルやガム)、繊維質の多いもの(肉やリンゴなど)は装置に絡まったり、破損の原因になったりすることがあります。これらの食材を避けるか、小さく刻む、煮込んで柔らかくするなど、調理方法を工夫することで、お子さまがストレスなく食事を楽しめるように配慮してあげてください。栄養バランスが偏らないように、様々な食材を取り入れる工夫も大切です。
矯正器具のケア方法
矯正治療中は、装置の周りに食べかすが残りやすく、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。特に小学校低学年のお子さまの場合、一人で完璧な歯磨きをすることは難しいことが多いです。そのため、保護者の方のサポートが非常に重要になります。
毎食後の歯磨きは、お子さまに「しっかり磨こうね」と声かけをし、特に寝る前には仕上げ磨きをしてあげましょう。タフトブラシ(先端が細いブラシ)や歯間ブラシ、デンタルフロスなど、矯正治療中に役立つ清掃用具を上手に活用することで、装置の周りの磨きにくい部分もきれいに保つことができます。一緒に鏡を見ながら、どこに磨き残しがあるかを確認し、正しい磨き方を教えてあげることで、お子さまも自分で意識して磨く習慣が身につくでしょう。
心理的なサポート
歯列矯正は数年かかることもあり、お子さまが途中で治療を嫌がったり、モチベーションが下がったりすることもあります。装置の見た目を気にしたり、痛みや不便さを感じたりするのは自然なことです。そのような時には、お子さまの気持ちに寄り添い、「大変だね」「頑張っているね」と共感の言葉をかけてあげることが大切です。
治療が進むにつれて歯並びが少しずつきれいになっていく様子を一緒に写真で確認したり、「歯がきれいになったら、もっと素敵な笑顔になるね」といったポジティブな言葉で励まし続けたりしましょう。定期的に治療のゴールを親子で確認し合うことも、モチベーション維持につながります。保護者の方が一番の理解者として、温かく前向きなサポートを続けることが、お子さまが治療を乗り越えるための大きな支えになりますよ。
歯列矯正で得られるメリット
歯列矯正は、時間や費用、そしてお子さん自身の努力が必要な長い道のりです。しかし、その先に待っているのは、単に見た目の改善だけではありません。お子さんの心身の健康、ひいては生涯にわたる生活の質の向上につながる、かけがえのないメリットがたくさんあります。
このセクションでは、矯正治療を乗り越えた後に得られる具体的な恩恵について詳しくご紹介します。保護者の皆さんが、お子さんの将来への大切な投資として、矯正治療の価値を再認識するきっかけになれば幸いです。
健康的な噛み合わせの獲得
矯正治療の最も重要な目的の一つは、健康的な噛み合わせを獲得することです。上下の歯が正しく噛み合うことで、食べ物を効率よく噛み砕けるようになります。これは、消化吸収を助け、胃腸への負担を軽減することにもつながります。
また、正しい噛み合わせは、特定の歯に過度な負担がかかることを防ぎます。これにより、歯のすり減りやひび割れ、歯周病のリスクを減らすことができます。さらに、顎の関節への負担も軽減されるため、将来的な顎関節症といった顎のトラブルを予防することにもつながります。このように、噛み合わせの改善は、お子さんの長期的な健康維持に大きく貢献するのです。
自信を持てる笑顔
歯並びが整うことで、お子さんは見た目のコンプレックスから解放され、自信を持てるようになります。これまで人前で口元を隠していたお子さんも、矯正治療によってきれいになった歯並びを気にすることなく、心から笑えるようになるでしょう。
笑顔が増えることは、お子さんの自己肯定感を高め、社交性を育む上でも非常に大切です。積極的にコミュニケーションが取れるようになる、自信を持って発表できるなど、学校生活や習い事、友人関係においてもポジティブな変化が期待できます。見た目の改善は、お子さんの内面の成長にもつながる大きなメリットと言えます。
長期的な口腔健康の向上
歯並びが整うことで、毎日の歯磨きが格段にしやすくなります。歯が重なり合っている部分や、装置が邪魔をして磨きにくかった部分も、矯正によって解消されるため、歯垢や食べかすが残りにくくなります。
その結果、虫歯や歯周病になるリスクを大幅に減らすことができます。子どもの頃に正しい歯並びと噛み合わせを手に入れることは、単に見た目をきれいにするだけでなく、生涯にわたってご自身の歯で健康に過ごすための「最高の予防歯科」と言えるでしょう。矯正治療は、お子さんの長期的な口腔健康を維持するための、賢明な投資なのです。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
高橋 衛 | Takahashi mamoru
岩手医科大学歯学部卒業後、岩手医科大学歯学部口腔外科第二講座入局し、
医療法人 高橋衛歯科医院設立 理事長就任、MAMO IMPLANT CLINIC MALIOS 開設
【所属】
・日本歯科医師会
・岩手県歯科医師会
・盛岡市歯科医師会
・歯科医師臨床研修指導歯科医
・岩手県保険医協会
・日本口腔外科学会
・日本口腔インプラント学会
・EUROPEAN ASSOCIATION FOR OSSEOINTEGRATION
・AMERICAN ACADEMY PERIODONTOLOGY
・岩手医科大学歯学会
・デンタルコンセプト21 会員
・日本歯科東洋医学会
・JIADS Club 会員
・P.G.I Club 会員
・スピード矯正研究会 会員
・床矯正研究会 会員
・近代口腔科学研究会 会員
【略歴】
・岩手医科大学歯学部 卒業
・岩手医科大学歯学部口腔外科第二講座 入局
・「高橋衛歯科医院」 開業
・「MAMO IMPLANT CLINIC MALIOS」 開業
盛岡市で評判・インプラント治療なら
『マモ インプラントクリニックマリオス』
住所:岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9−1
TEL:019-645-6969