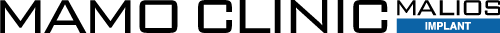「うちの子の歯磨きは、いつから始めれば良いの?」「ちゃんと磨けるかな」といった赤ちゃんの歯に関するお悩みは、多くの保護者の方が抱える共通の不安ではないでしょうか。この記事では、赤ちゃんの歯磨きを始める適切なタイミングから、お子さんが嫌がらずに楽しくオーラルケアを続けられる具体的な方法、さらには毎日の歯磨きをサポートするアイテムの選び方まで、分かりやすく丁寧にご紹介します。お子さんの大切な歯の健康を守り、将来にわたって健やかな口元を育むための第一歩を踏み出しましょう。
赤ちゃんの歯磨きはいつから始めるべき?
赤ちゃんの歯磨きはいつから始めれば良いのか、多くの保護者の方が悩むことでしょう。このセクションでは、赤ちゃんの歯磨きを開始する適切なタイミングを詳しく解説します。乳歯が生え始めたらすぐにケアを始めるべき理由や、その重要性についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
乳歯が1本でも生えたらスタートの合図
赤ちゃんの歯磨きは、最初の乳歯が1本でも生えてきたタイミングで始めるのが理想的です。個人差はありますが、一般的に生後6ヶ月から8ヶ月頃がその目安とされています。お子さまのお口の中に小さな白い歯の頭が見え始めたら、それがオーラルケアをスタートさせる合図と捉えてください。
この時期からのケアは、単に口の中を清潔にするだけでなく、将来の永久歯の健康や正しい歯並びにも大きく影響します。乳歯の段階から適切なケアを習慣づけることで、虫歯予防はもちろんのこと、お子さまの健やかな成長をサポートすることに繋がります。
歯が生える前からできる!口の中に触れる習慣づけ
本格的な歯磨きを始める前の準備として、歯が生える前から赤ちゃんの口の中に触れる習慣をつけておくことが非常に大切です。例えば、授乳後や離乳食の後に、清潔なガーゼや綿棒を指に巻き、優しく赤ちゃんの歯ぐきや舌に触れてみましょう。
この「お口に触れる練習」は、赤ちゃんが口の中に物が入ることに慣れるための第一歩となります。早い段階からお口に触れられることに抵抗がなくなると、いざ歯ブラシを使って歯磨きを始める際に、よりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。この時間は、親子の大切なスキンシップとしても楽しんでみてください。
なぜ早めのケアが大切?乳歯が将来の歯並びや健康を左右する
「乳歯はいずれ永久歯に生え変わるから、そこまで神経質にならなくても良いのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、乳歯の時期からの丁寧なケアは、お子さまの将来の歯並びや健康に深く関わるため、非常に重要なのです。
まず、乳歯は大人の歯(永久歯)と比較して、エナメル質が半分ほどの薄さしかありません。そのため、酸に対する抵抗力が弱く、虫歯になりやすいという特徴があります。一度虫歯になると進行も早いため、早期からの予防と発見が何よりも大切になります。
さらに、乳歯は永久歯が生えてくるためのガイド役も担っています。乳歯が虫歯で早期に失われたり、治療されずに放置されたりすると、永久歯の生えるスペースが不足し、将来的な歯並びの乱れに繋がる可能性があります。このように、乳歯の健康は、お子さまの成長における土台作りと捉え、早めのケアを心がけましょう。
【月齢・年齢別】赤ちゃんの歯磨きの進め方と仕上げ磨きのコツ
このセクションでは、赤ちゃんの成長段階に合わせた歯磨きの具体的な進め方について詳しくご説明します。歯が生える前から2歳頃までのステップごとのケア方法や、保護者の方が行う「仕上げ磨き」のコツをわかりやすく解説いたします。お子さまの月齢に合った項目を参考に、日々のオーラルケアにお役立てください。
STEP1:歯が生える前(〜生後5ヶ月頃)ガーゼで口を拭く練習
赤ちゃんの歯磨きの準備として、歯が生える前から始めていただきたいのが、口の中に触れる習慣づくりです。生後5ヶ月頃までのまだ歯が生えていない時期から、授乳後などに清潔なガーゼや綿棒を湿らせて、赤ちゃんの口の中や歯ぐきを優しく拭いてみましょう。これは、離乳食が始まることで口の中に食べかすが残りやすくなるため、清潔を保つ目的もあります。
このガーゼでの拭き取りは、歯が生えてからの本格的な歯磨きへとスムーズに移行するための大切なステップになります。赤ちゃんが口に何かが触れることに慣れることで、歯ブラシへの抵抗感を減らし、その後の歯磨きを嫌がりにくくする効果が期待できます。優しく楽しく、親子のスキンシップの一環として続けてみてくださいね。
STEP2:歯の生え始め(生後6ヶ月頃〜)歯ブラシに慣れる
乳歯が1本、2本と生え始める生後6ヶ月頃からは、「歯ブラシに慣れること」を目標にケアを進めていきましょう。まずは赤ちゃん用の安全な歯ブラシ、例えば喉突き防止のプレートが付いているものなどを与えて、おもちゃのように持たせて遊ばせてみてください。保護者の方が優しく赤ちゃんの歯に歯ブラシの毛先を触れさせて、歯ブラシが口の中に入ってくる感触に慣れさせてあげるのも良いでしょう。
この時期は、まだ完璧に磨くことよりも、歯ブラシを嫌がらないようにすることが大切です。歯ブラシを楽しいものだと認識してもらうことで、今後の歯磨き習慣の定着につながります。遊びの延長として、ポジティブな気持ちで歯ブラシとの最初の出会いをサポートしてあげてください。
STEP3:上下の前歯が生えそろう(1歳頃〜)仕上げ磨きを習慣に
上下の前歯がほとんど生えそろう1歳頃からは、保護者の方による「仕上げ磨き」を毎日の習慣として取り入れることが非常に重要になります。この時期の赤ちゃんは、まだ自分で上手に歯を磨くことはできませんので、保護者の方がしっかりと磨いてあげる必要があります。
仕上げ磨きを効果的に行うためには、赤ちゃんが安定して、かつ口の中が見やすい姿勢が大切です。例えば、保護者の膝の上に赤ちゃんの頭を乗せて仰向けに寝かせる「膝枕の姿勢」は、口の中がよく見えて磨き残しを防ぎやすいのでおすすめです。この姿勢で、歯ブラシを優しく歯に当て、軽い力で小刻みに振動させるように動かして磨きましょう。
特に、歯と歯ぐきの境目や、歯と歯の間、そして前歯の裏側は汚れがたまりやすい部分ですので、意識して丁寧に磨いてあげてください。この時期から毎日欠かさず仕上げ磨きを行うことで、虫歯予防の基礎を築くことができます。
STEP4:奥歯が生えてくる(1歳半頃〜)本格的な歯磨きへ
1歳半頃からは、食べ物をすり潰すための奥歯(乳臼歯)が生え始めます。奥歯は溝が複雑な形をしており、食べかすが非常に詰まりやすく、虫歯のリスクが特に高い部位です。この時期から、より本格的な歯磨きが必要になりますので、保護者の方の仕上げ磨きも一層丁寧に行うことが大切です。
仕上げ磨きの際には、奥歯の複雑な溝に毛先をしっかりと入れ込むように意識して磨きましょう。また、奥歯と奥歯の間も食べかすが残りやすく、虫歯になりやすいポイントです。歯ブラシだけでは届きにくい場合は、デンタルフロスなどの補助清掃用具も活用することをおすすめします。
この時期は、歯の生え方や成長に合わせて、歯ブラシの選び方や磨き方も見直していくと良いでしょう。奥歯までしっかり届くヘッドの小さな歯ブラシや、保護者の方が持ちやすい仕上げ磨き専用の歯ブラシなどを活用して、効率的かつ確実に汚れを落とすことを目指しましょう。
STEP5:自分で磨きたがる時期(2歳頃〜)ひとり磨きと仕上げ磨き
2歳頃になると、多くのお子さんが自分で歯ブラシを持ちたがったり、保護者の真似をして磨きたがったりするようになります。この「自分でやりたい」という自立心を育む大切な時期ですので、まずは自由に歯ブラシを持たせて「ひとり磨き」の時間を作ってあげましょう。鏡を見ながら一緒に磨いたり、「あーんして」と声をかけたりしながら、歯磨きの楽しさを伝えてあげてください。
しかし、お子さん自身のブラッシングだけでは、まだ奥歯や歯の裏側など、細かい部分の汚れを完全に落とすことは困難です。そのため、ひとり磨きの後に必ず保護者の方が「仕上げ磨き」で完璧に磨き上げることが不可欠です。ひとり磨きでお子さんの歯磨きへの関心を育て、仕上げ磨きで虫歯を予防するという、二段階のアプローチがこの時期の理想的なケア方法となります。
仕上げ磨きの際は、お子さんが自分で磨ききれていない部分、特に奥歯の溝や歯と歯の間、そして歯ぐきの境目を意識して、丁寧に磨いてあげてください。この丁寧なケアが、お子さんの健康な永久歯への土台を築くことになります。
仕上げ磨きはいつまで?小学校中学年頃まで続けよう
多くの保護者の方が「仕上げ磨きはいつまで続ければよいのだろう」と悩まれるかと思いますが、一般的にはお子さんが自分で上手に歯磨きができるようになる、小学校中学年(9〜10歳)頃まで続けるのが理想的です。
なぜなら、小学校低学年頃のお子さんの手先の器用さでは、奥歯の複雑な溝や歯と歯の間、そして歯の裏側など、磨き残しになりやすい部分を完璧に清掃することは難しいからです。また、この時期は乳歯から永久歯への生え変わりの時期でもあり、歯並びが複雑になるため、さらに磨きにくくなる傾向があります。仕上げ磨きは、単に虫歯を予防するだけでなく、保護者の方が毎日お子さんのお口の中の健康状態をチェックする貴重な機会でもあります。お子さんの成長に合わせて、根気強く仕上げ磨きを続けてあげてくださいね。
赤ちゃんのための歯ブラシ・歯磨き粉の選び方
赤ちゃんの歯の健康を守るためには、毎日のオーラルケアに使う歯ブラシや歯磨き粉選びが非常に重要になります。安全かつ効果的にケアを進めるためには、お子様の成長段階に合わせた適切な道具を選ぶことが大切です。このセクションでは、赤ちゃんのための歯ブラシと歯磨き粉の具体的な選び方のポイントをご紹介します。
歯ブラシの選び方のポイント
歯ブラシを選ぶ際には、お子様自身が使う「本人磨き用」と、保護者の方が使う「仕上げ磨き用」とで、それぞれ異なるポイントがあります。それぞれの役割と目的に応じて、適切な形状や機能を持った歯ブラシを選ぶことが、効果的なケアに繋がります。
赤ちゃん用歯ブラシ(本人磨き用)
赤ちゃん自身が自分で歯ブラシを持ち始める時期の「本人磨き用」歯ブラシは、何よりも「安全性」と「使いやすさ」を重視して選びましょう。
まず、お子様の月齢に合った「ヘッドのサイズが小さいもの」を選びます。これは、小さなお口の中でも歯ブラシがスムーズに動かせ、お口の中を傷つけにくいようにするためです。次に、毛の硬さは必ず「やわらかめ」を選んでください。歯ぐきや生え始めたばかりの乳歯を優しく磨けるように配慮されています。さらに、お子様が安全に使えるよう、「喉突き防止のプレート」が付いているものや、転倒時などに衝撃を吸収する「ハンドルが曲がるタイプ」を選ぶと安心です。これらの特徴は、赤ちゃんが歯ブラシを遊びながら口に入れることが多いこの時期に、安全に歯ブラシに慣れる練習ができるようにするために非常に重要となります。
仕上げ磨き用歯ブラシ
保護者の方が行う「仕上げ磨き用」歯ブラシは、赤ちゃんのお口の隅々まで磨き残しなくきれいに磨き上げることが目的です。そのため、本人磨き用とは異なる特徴を持った歯ブラシを選びましょう。
まず、奥歯の奥までしっかり届くように「ヘッドが非常にコンパクトなもの」を選んでください。次に、保護者の方が持ちやすく、鉛筆を持つように安定して操作できる「ストレートで長めのハンドル」がおすすめです。これにより、細かな力加減で正確に歯ブラシを動かせます。また、歯と歯ぐきの境目など、汚れが溜まりやすい部分を狙いやすいように「毛先が細くなっているもの」を選ぶと、より効果的にプラークを除去できます。これらの特徴を備えた歯ブラシを選ぶことで、お子様のデリケートな乳歯を優しく、かつしっかりとケアすることが可能になります。
歯磨き粉は必要?選び方とフッ素濃度
「赤ちゃんに歯磨き粉は必要なのだろうか」と疑問に思われる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。結論から言うと、虫歯予防効果のあるフッ素が配合された歯磨き粉の使用は、非常に推奨されています。フッ素は歯を強くし、虫歯菌の活動を抑える働きがあるため、毎日のケアに取り入れることでお子様の歯を虫歯から守る手助けになります。
ただし、お子様の年齢によって適切なフッ素の濃度や使用量が異なりますので、選び方を間違えないことが大切です。次項では、年齢に応じたフッ素濃度と使用量の目安について詳しく見ていきましょう。
年齢に応じたフッ素濃度と使用量の目安
フッ素は虫歯予防に効果的ですが、その濃度と使用量は年齢によって適切に調整する必要があります。公的なガイドラインに基づいた年齢別の目安は以下の通りです。
6ヶ月〜2歳:フッ素濃度500ppmF、使用量は切った爪程度の少量(米粒大)
3歳〜5歳:フッ素濃度500ppmF、使用量はグリーンピース大(5mm程度)
6歳以上:フッ素濃度1000ppmF(〜1500ppmF)、使用量は歯ブラシの毛先半分〜全体(1cm程度)
これらの目安を参考に、お子様の年齢に合った歯磨き粉を選び、適切な量を使用することで、フッ素の虫歯予防効果を最大限に引き出すことができます。
赤ちゃんが嫌がらない味や成分を選ぼう
赤ちゃんが歯磨きを嫌がらないようにするためには、歯磨き粉の味や成分選びも重要なポイントです。赤ちゃんや幼児は味覚が非常に敏感なため、大人用の歯磨き粉によくあるミントのような刺激の強いフレーバーは避けるべきです。子供が好むいちご味やぶどう味といった甘いフルーツフレーバーのものが多く市販されていますので、お子様が喜んで受け入れてくれる味を選ぶと、歯磨きの時間を楽しくするきっかけになります。
また、歯磨き粉の成分にも注目しましょう。泡立ちが多いと磨けていると錯覚しやすく、実際には汚れが残っていることもありますので、「低発泡」や「発泡剤無配合」のものがおすすめです。さらに、乳歯はデリケートなので、歯を傷つけないように「研磨剤無配合」や「低研磨性」と表示されているものを選ぶと安心です。
デンタルフロスなど補助清掃用具はいつから?
歯ブラシだけでは、歯と歯の間など狭い隙間の汚れを完全に除去することは難しい場合があります。このような歯ブラシが届きにくい部分のケアには、デンタルフロスなどの補助清掃用具の活用が効果的です。一般的に、歯と歯が隣り合って隙間がなくなった時期、目安としては奥歯が生えそろう1歳半から2歳頃が、デンタルフロスの使用を開始するタイミングとされています。
お子様が小さいうちは、保護者の方が仕上げ磨きの際にデンタルフロスを使ってあげましょう。子供用のデンタルフロスには、持ち手が付いていて使いやすい「フロスピック」というタイプもあります。これらを活用することで、虫歯になりやすい歯と歯の間の汚れもしっかりと取り除き、より効果的な虫歯予防に繋がります。
子供が歯磨きを嫌がる!親子で楽しむための5つのコツ
お子さんの歯磨きをしようとすると、泣いて嫌がったり、口を閉じてしまったりして困ることはありませんか?多くのご家庭で「歯磨きイヤイヤ期」は共通の悩みですよね。このセクションでは、叱ったり無理やり押さえつけたりするのではなく、ちょっとした工夫で歯磨きの時間を「親子で楽しむ時間」に変えるための具体的な方法を5つのコツとしてご紹介します。ぜひ、お子さんと一緒に笑顔でオーラルケアを続けられるヒントを見つけてください。
1. 歯磨きの時間を決めて生活リズムに組み込む
お子さんが歯磨きを嫌がる場合、まずは歯磨きの時間を毎日同じにする工夫をしてみましょう。例えば、朝食の後や寝る前など、決まったタイミングで歯磨きを行うことで、お子さんは次に何が起こるかを予測できるようになります。この予測可能性が、お子さんの不安を和らげ、安心して歯磨きを受け入れる土台となります。
歯磨きを生活リズムの一部として定着させると、「歯磨きは当たり前のこと」としてお子さんの中に自然と組み込まれていきます。日によって時間がバラバラだと、お子さんは次に何をするのか分からず不安を感じやすくなりますが、規則的な習慣にすることで、歯磨きに対する心の準備が整いやすくなりますよ。
2. 歯磨きに関する絵本や歌で楽しい雰囲気を作る
お子さんが歯磨きを嫌がるときは、歯磨きを楽しいイベントに変える工夫が有効です。歯磨きをテーマにした絵本を読み聞かせたり、歯磨きの歌や動画を一緒に見ながら磨いたりするのはいかがでしょうか。お子さんが好きなキャラクター、例えば「しまじろう」などのコンテンツを活用するのも効果的です。
これらの楽しい仕掛けを取り入れることで、歯磨きに対する「嫌なこと」というネガティブなイメージを払拭し、「楽しいこと」というポジティブなイメージへと変えていくことができます。遊びの延長として歯磨きを取り入れることで、お子さんの抵抗感を減らし、自ら歯磨きに興味を持つきっかけ作りにも繋がります。
3. 保護者が楽しそうに歯磨きする姿を見せる
お子さんは、大人の真似をしたがるものです。保護者の方が楽しそうに、気持ちよさそうに自分の歯を磨く姿をお子さんに見せることは、歯磨きへの関心を高める上で非常に効果的です。お子さんの前で「シャカシャカ、きれいになるの気持ちいいね」「わぁ、歯がピカピカになったよ!」といったポジティブな言葉をかけながら、ご自身の歯磨きを実践してみてください。
保護者の楽しそうな姿やポジティブな声かけは、お子さんの「自分もやってみたい」という意欲を引き出します。また、歯磨きが「楽しいもの」「気持ちの良いもの」という印象を与えることで、お子さん自身が自発的に歯磨きにチャレンジするきっかけにもなりますよ。
4. 終わったらたくさん褒めてあげる
お子さんが歯磨きを頑張った後には、たとえ短時間だったとしても、たくさん褒めてあげることがとても大切です。少しでもお口を開けてくれたら「お口あーんできたね!えらい!」、歯磨きが終わったら「ピカピカになったね、すごい!」など、大げさなくらいに褒めてあげましょう。この「褒める」という行為は、お子さんにとって大きな喜びとなり、次の歯磨きへの意欲に繋がります。
歯磨きが終わると良いことがある、という経験を積み重ねることで、お子さんは歯磨きをポジティブに捉えるようになります。お子さんの達成感や自己肯定感を育みながら、歯磨きが楽しい習慣となるように、ぜひ惜しみない愛情で褒めてあげてください。
5. 痛くない正しい仕上げ磨きの姿勢と磨き方をマスターする
お子さんが歯磨きを嫌がる原因の一つに、物理的な不快感や「痛み」があります。お子さんに恐怖心を与えないためには、保護者の方が正しい姿勢と優しい磨き方をマスターすることが非常に重要です。
仕上げ磨きをする際には、お子さんを保護者の膝の上に仰向けに寝かせる姿勢がおすすめです。この姿勢だと、お子さんの口の中全体がよく見え、奥歯までしっかりと歯ブラシを届かせることができます。また、お子さんの頭が安定するため、安全に磨くことが可能です。
歯ブラシは強い力でゴシゴシと磨くのではなく、軽い力で小刻みに振動させるように優しく動かすのがポイントです。歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に当て、汚れをかき出すように丁寧に磨きましょう。痛くない、気持ちの良い歯磨きを心がけることで、お子さんは歯磨きに対して前向きな気持ちを育んでいけるはずです。
かかりつけ歯科医院を見つけよう!赤ちゃんの歯科検診
赤ちゃんの健やかな歯を育むためには、ご家庭での毎日のケアはもちろん大切ですが、歯科医院での専門的なケアも非常に重要です。乳歯が生え始めたら、ぜひ信頼できる「かかりつけ歯科医院」を見つけて、定期的な歯科検診を始めましょう。定期的な検診は、虫歯の早期発見・早期治療につながるだけでなく、保護者の皆さまが抱える日頃の不安を解消し、お子さま一人ひとりに合わせた専門的なアドバイスをもらう絶好の機会となります。
初めての歯科検診はいつがいい?
赤ちゃんの初めての歯科検診は、一般的に最初の乳歯が生えてきたタイミング、具体的には生後6ヶ月から1歳頃までに受診することをおすすめします。この時期の受診は、虫歯の治療が主な目的ではありません。むしろ、赤ちゃんが歯科医院の雰囲気に慣れる良い機会となり、保護者の方が日々の歯磨き方法や注意点について専門家からアドバイスを受けることが主な目的です。
何かトラブルが起きてから初めて歯科医院を訪れるのではなく、まだ問題が起きていない時期から通い始めることで、お子さまが歯科医院に対して良い印象を持ちやすくなります。また、早期から専門家の目でチェックしてもらうことで、将来的な虫歯リスクを未然に防ぎ、お子さまの歯の健康を長く守ることにつながります。
歯科医院でできる虫歯予防
歯科医院では、ご家庭での歯磨きだけでは難しい専門的な虫歯予防処置を受けることができます。その代表的なものが「フッ化物歯面塗布」、いわゆる「フッ素塗布」です。歯科医院で行うフッ素塗布では、ご家庭で使う歯磨き粉よりも高濃度のフッ素を歯に直接塗布します。
フッ素には、歯の表面のエナメル質を強化し、酸に溶けにくい状態にする効果や、再石灰化を促進して初期の虫歯を修復する効果があります。この処置を定期的に行うことで、歯質がより一層強化され、虫歯になりにくい強い歯を育てることができます。定期的なフッ素塗布は、お子さまの歯を虫歯から守る上で非常に有効なプロフェッショナルケアと言えるでしょう。
家庭でのケアについて専門家に相談しよう
歯科検診は、お子さまの歯のチェックだけでなく、保護者の方が日頃抱えている歯に関する疑問や不安を解消する貴重な場でもあります。「うちの子の歯磨きは、これで正しいのでしょうか?」「歯並びが少し気になるのですが、大丈夫でしょうか?」といった具体的な質問を、歯科医師や歯科衛生士に直接相談してみましょう。
専門家は、お子さまの成長段階やお口の状態に合わせて、個別の状況に即した適切なアドバイスをしてくれます。例えば、歯ブラシの選び方、仕上げ磨きのコツ、食生活の注意点など、日々のケアに役立つ具体的な情報が得られるでしょう。このような専門家との連携を通じて、保護者の方も安心して日々のオーラルケアに取り組めるようになり、お子さまの健やかな成長をサポートできます。
まとめ:毎日のオーラルケアを習慣化し、親子の時間をもっと楽しく
赤ちゃんのオーラルケアは、保護者の方にとって多くの疑問や不安が伴うものかもしれません。しかし、これまでお伝えしてきたように、いくつかのポイントを押さえれば、決して難しいことではありません。
最も大切なのは、乳歯が1本でも生えたらすぐにケアを始めることです。そして、赤ちゃんの成長段階に合わせて、適切な歯ブラシと歯磨き粉を選び、毎日の生活リズムに歯磨きを習慣として組み込んでいきましょう。お子さまが歯磨きを嫌がる時期は、絵本や歌を取り入れたり、保護者の方が楽しそうに磨く姿を見せたり、終わったらたくさん褒めてあげたりと、工夫を凝らして楽しい時間に変えることが成功の秘訣です。また、痛みを感じさせない正しい仕上げ磨きの姿勢や磨き方をマスターすることも重要です。
さらに、家庭でのケアと並行して、乳歯が生えたら信頼できるかかりつけ歯科医院を見つけ、定期的な歯科検診を始めることをおすすめします。歯科医院では、フッ素塗布のような専門的な虫歯予防処置が受けられるだけでなく、日々のケアで生じる疑問や不安について、専門家から直接アドバイスをもらうことができます。
赤ちゃんの歯の健康を守ることは、将来の健やかな成長の土台を築く大切な取り組みです。大変だと感じる日もあるかもしれませんが、歯磨きの時間は親子のコミュニケーションを深める貴重な時間でもあります。ぜひ、前向きな気持ちで毎日のオーラルケアに取り組み、お子さまの笑顔と健康を育んでいきましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
高橋 衛 | Takahashi mamoru
岩手医科大学歯学部卒業後、岩手医科大学歯学部口腔外科第二講座入局し、
医療法人 高橋衛歯科医院設立 理事長就任、MAMO IMPLANT CLINIC MALIOS 開設
【所属】
・日本歯科医師会
・岩手県歯科医師会
・盛岡市歯科医師会
・歯科医師臨床研修指導歯科医
・岩手県保険医協会
・日本口腔外科学会
・日本口腔インプラント学会
・EUROPEAN ASSOCIATION FOR OSSEOINTEGRATION
・AMERICAN ACADEMY PERIODONTOLOGY
・岩手医科大学歯学会
・デンタルコンセプト21 会員
・日本歯科東洋医学会
・JIADS Club 会員
・P.G.I Club 会員
・スピード矯正研究会 会員
・床矯正研究会 会員
・近代口腔科学研究会 会員
【略歴】
・岩手医科大学歯学部 卒業
・岩手医科大学歯学部口腔外科第二講座 入局
・「高橋衛歯科医院」 開業
・「MAMO IMPLANT CLINIC MALIOS」 開業
盛岡市で評判・インプラント治療なら
『マモ インプラントクリニックマリオス』
住所:岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9−1
TEL:019-645-6969